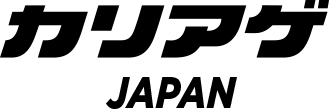#02 被災したM
鬼怒川の氾濫
かつて暮らした水海道のまちが被災地になってから、1年が経つ。
2015年9月10日、私はマンションの一室でテレビを見て、愕然としたのだった。そのとき、鬼怒川の防波堤が決壊し、常総市に甚大な浸水被害が出ているとして、緊迫した報道がなされていた。空撮ではもはや、それがどこだかわかる状態ではなかった。
合併してできた市だから、常総市と言われても、水海道が含まれるのかどうか、なかなかピンと来なかった。まさかね、とどこかで思っていた。やっと、それは自分が育ったあのまちで起きているのだと分かったのは、小さな橋のすぐ脇にあの頃からある、家具店の前から中継している映像だった。人物を映し出すほどカメラが寄らないと、まちのディテールが見えないくらい、どこもかしこも土色の水で溢れかえっていた。中継レポーターの背景は、私の通学路だった。
水海道を離れて20年以上が経っていた。それまでの間に、時折親の顔を見に行く度、水海道が寂しくなっていくさまを横目で見ていたものの、私は仮にも自分が育った町が、目に見えて痩せ細ることについて、自分でも驚くくらい、何とも思っていなかった。こうなることは子どもの頃から、うすうす勘付いていた気すらした。あの頃から、働いたり学んだり、遊んだり買い物をしたりするために、他の都市エリアに出て行く人の姿を見ていたから、自分の町は、ひとの活動にとって物足りないところなのだ、ということもわかっていた。
でもそれよりもっと幼心に気にかかっていたのは、例えば商店の看板がいくら古びても更新されないことだったり、ブタクサだらけの荒れ地がいつまでたってもブタクサだらけの荒れ地であることだったり、壊れかけの空き家がいつまでたっても壊れかけのまま在り続けていることだったり、砂利敷きの駐車場の片隅にいつ見ても1ミリも動かない廃車が何年も放置されていたり、といった、それなりの年月をかけて日々脳裏に刷り込まれていく、ごくごくありきたりな風景への、漠然とした違和感にあった。
当時はなにも言語化できていなかったけれど、今思うと繰り返し見続けていたあの町の風景は、要するにそこがどうなろうと、誰も、ちっとも手入れをしない、もしくはできない状態であることを、私に毎日、知らしめていたのだった。私はだから、わかっていた。ここはもはや、愛されていない場所なのだ、と。
そこでたまたま展開した人付き合いを愛する人も、そこでたまたま望める空の色を愛する人も、いるかもしれない。だけど誰も、作為的かつ具体的に、まちに手を入れていない。私はその証拠としての風景を、何年も眺めながら育っていたのだった。目にする綻びのひとつひとつがどんなにヤバい予兆であるかを悟るには、あまりに人生経験がなかったから、なるほどまちとは、田舎とはそういうものなのだ、と思うしかなかった。明らかに全体的に、朽ちていっている。そんなまちがやがてどうなるか、いくら子どもでも、そうそう外れた予想図など浮かぶわけもなかった。

実家がなくなった
実はこの20年以上もの中で、まちと私との関係も、決定的に変化した。4年前、このまちで病院を経営していた父親が死去し、私たち田中家の住戸でもあった病院は、人手に渡ったのだった。実家は、なくなった。私はいよいよこのまちに何の用もなくなっていたし、それを当然として暮らしていた。父を亡くしたことも、実家を失ったことも、自分ではもっともっと悲しむと思っていた。
水海道が水浸しになっている映像を見ても、どんな気持ちになるべきなのか、そもそも準備ができていなかった。私とはもう、何の縁もない土地なのだ。何が流されて何が失われても、どう感じればいいのか、わからない。とりあえず母親に電話をかけて状況を聞き、こころの奥にそわそわとした混乱を持て余しながら、日常生活をやり過ごした。元実家だったあの病院が、この洪水で甚大な被害を受けたこと、そして復興のためのクラウドファンディングに挑戦していることを偶然知ったのは、それから間もなくのことだった。
被害状況にも改めて驚いたけれど、それよりいい意味で驚いたのは、病院のインターネットを介した告知、広報だった。父が経営していた時代ではあり得ないくらい、ハイテクで現代的な活動だ。お父さんの病院、いい会社に買ってもらえたんだな。そんなことを微笑ましく思いながら、ひとりの他人として、ひと口分の参加ボタンをクリックした。このワンクリックが、まさかあのまちと再会するきっかけになろうとは。

Mとの再会
病院のクラウドファンディングは見事に成功し、やがて被害を受けた1階部分の改修をお披露目する会が開かれるというので、いち参加者として、私は本当に久しぶりに、水海道を訪れた。水の引いたまちは泥まみれで、建物やガードレールの所々が水圧で変形し、見渡す限り乾いた土埃で白んでいた。どの家も屋内にあったあらゆるものを外に出して、マスク姿の人々が片付け作業に追われていた。子どもの頃に遊んだ近所の公園は臨時のゴミ置き場になっていて、敷地内がパンパンになってもなお持ち込まれ続けるゴミが、うずたかく積み上がっていた。いつにも増して、懐かしさはなかった。もはやそこがどこであろうと、被災地だと認識せざるを得ない風景だった。
病院に到着し、白衣姿の院長を見かけたので、声をかけた。握手しながら、院長は「お父さんの病院、護りましたよ」と言った。その言葉が、意外だった。水害を知った時から無自覚のうちにどこか張り詰めていたのだろうか、父を思ったのだろうか、私はその瞬間、堰を切ったように嗚咽した。安心したような、許されたような気持ちだった。そして戸惑いと無関心しか自覚できていなかった、このまちと自分との関係に、これからは落ち着いて向き合える気がした。好きとか嫌いとかではなく、確かに自分に紐づく、あるひとつのまちとして。
実際、この災害によって、向き合い直さねばならない理由もできていた。かつて病院の職員が住むために使っていた、水海道にある一軒の住戸は今、私の名義になっているのだ。水害を受けるほんの数ヶ月前に、権利が書き換えられたばかりだった。私は現在、ただでさえ寂れゆく小さな町で、さらに浸水被害により被害を受け、住まい手を失った、小さな空き家の初心者大家なのだった。


田中元子(たなか・もとこ)
ground level代表。1975年茨城県生まれ。独学で建築を学ぶ。2004年mosaki共同設立。建築コミュニケーターとして、執筆、プロデュース、企画など、さまざまに活動。2010年より「けんちく体操」に参画。2014年、『建築家が建てた妻と娘のしあわせな家』(エクスナレッジ)を上梓。近年は「アーバンキャンプ」や「パーソナル屋台」など、ダイレクトにまちや都市、ひとに関わるプロジェクトに重点をシフトさせている。2016年より「グランドレベル」始動。(photo:kenshu shintsubo)
空き家について相談したい
「実家が空き家になった」「空き家の管理に困っている」「空き家を借りてほしい」など、
空き家の処遇にお悩みの方、お気軽にご相談ください。